この文章は、2022年1月17日〜2月6日に実施したオンライン配信イベント「Made in Japan YAMAGATA 1989-2021」に合わせて執筆されたエッセイを日本語訳したものです。
1995年3月20日、秋の山形国際ドキュメンタリー映画祭に向けて準備が進んでいた頃、日本は国内テロの衝撃を受けた。オウム真理教の5人のメンバーが、東京の地下鉄車内でサリンの入った袋の封を開けたのである。攻撃を受けた駅は、神楽坂にある映画祭東京事務所から数キロしか離れておらず、そこかしこが危険にさらされた。14人が亡くなり、5,000人以上の被害者が病院に運ばれ、事態は急速に大惨事になった。その春から夏にかけて、日常生活が一変したことを鮮明に覚えている。東京のゴミ箱はすべてテープで閉じられ使用できなくなってしまったので、映画祭事務所への行き帰りのあいだにポケットにいろいろなゴミ屑を溜めこむことになった。特にマスコミが捜査状況や教団の内実を大げさに報道したため、一般には恐怖が拡がっていた。
すべてはあまりに劇的に展開していたので、この経緯を追いかける勇敢な映画制作者はいないものだろうかと私は考えていたものだ。3年後、森達也の『A』(1998)、そして2001年の『A2』がその答えになった。森達也が発表したこれらの映画は、ダイレクト・シネマの一種である。彼は、カルト教団の周りのメディアの熱狂をビデオカメラで追いかけ、質問をするシーンではしばしば自身の姿を画面に映し込む。ところどころで彼は物事に対する自分の見方をそのまま描きだす。これらの映画、特に1作目は相当な驚きとともに迎えられた。森はどういうわけかオウムの指導者に気に入られ、警察とメディアに包囲された組織の内部を日本の観客に垣間見せてくれたのである。この映画は、カルトの活動や信仰の在り方、当局やマスコミの明らかに非倫理的な行動など、さまざまな疑問を投げかけている。これを出発点にして、森はドキュメンタリーとジャーナリズムの倫理の問題を中心にキャリアを積んでいった。
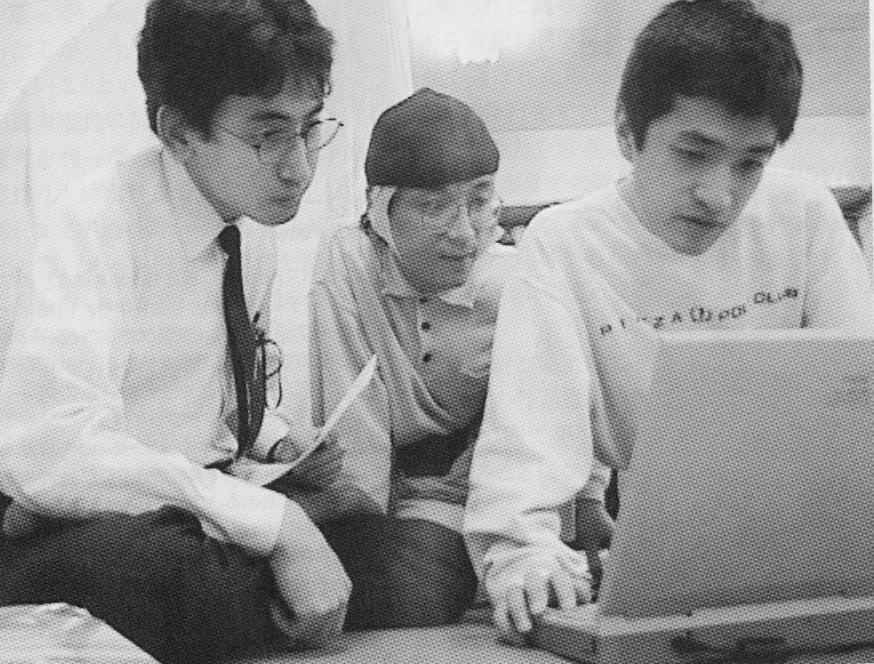
信じられないことだが、私は森達也がドキュメンタリー映画作家としての自分の仕事を軽視している発言を聞いたことがある。確かに、彼は40冊以上の本を書きあげ、テレビではジャーナリズムの倫理が前面に出るときはいつもコメンテーターとして出演している。しかし、彼の日本ドキュメンタリーへの貢献は否定することはできない。『A2』は彼の作品群に接近するためのよい出発点である。
森は立教大学に入学し、そこで黒沢清をはじめとする映画狂の学生たちと知り合った。黒沢の初期作品に出演してもいる。同じ頃、テレビ・ジャーナリズムの世界に入ったが、主要テレビ局の厳しさには耐えられないばかりか、怪しさを感じることもあったという。
オウム真理教の地下鉄テロ事件でそれが露呈する。事件の翌年、森はオウムの広報担当者である荒木浩に接触し、膨大なインタビューを行うことに成功した。それをもとにテレビ・ドキュメンタリー番組を制作しようとしたが、製作者側は荒木のインタビューを切り取り、従来の誇張された報道のなかに埋め込もうとするだけだった。そこで彼は、原一男の『ゆきゆきて神軍』(1987)の助監督からキャリアのスタートを切った安岡卓治プロデューサーと組み、『A』というタイトルの長編ドキュメンタリーに編集を仕上げていくことになったのである。
当時は、インディペンデントのドキュメンタリー作品の配給が困難な時代だった。戦後の自主上映会や企画団体のネットワークは、全国に拡がる独立系の映画館、いわゆるミニシアターへと姿を変えつつあった。その数は少なくまばらであり、ノンフィクションはあまり上映されていなかった。
技術的な障害もあった。当時はまだフィルムからビデオへの過渡期だった。映画祭の常連であるジョン・ジョストは、ちょうどデジタルキャプチャーに移行してそれを普及もさせようともくろんでいた頃で、森が『A』を完成させたのと同じとき、山形にフルデジタルの『ロンドンスケッチ』(1997)を応募していた。映画祭はコンペへの出品を認めたが、規定によりフィルム素材へ変換することが監督には求められた。ジョストはそのためのかかる3万ドルの資金がないと言ったが、映画祭は頑として譲らなかった(最終的にこの作品はコンペティション外で上映され、賞を獲得した)。1997年のYIDFFで『A』がコンペティション外で上映されたのにはこのような理由もあった。
森と安岡は、このビデオに対する深い偏見に立ち向かったのである。『A』と『A2』は荒削りである。カメラはほとんど手持ちで、時折風で音声が飛ぶというお粗末なものだ。照明はよく暗くなる。画質が低いので、終始どこかぼんやりしてみえる。結果的には、『A』は最初の公開時よりも、その後の方が多く見られている作品になった。2001年の『A2』になると状況はより改善している。その頃は山形でもフィルム変換を想定しないビデオ作品の応募を受け付け始めていた。『A2』はその年のインターナショナル・コンペティションで上映され、2つの賞の受賞を果たしたのである。
映画を新しいテクノロジーとみなしその変幻自在さを見る者が受けとめるとき、これらの作品は驚異的なものに映った。森はオウムの聖域とその外部の狂ったメディア業界の境界を自由に行き来している。これは映画内の記者会見の場面でいくたびもはっきりと描かれている。マスコミの一群がカメラを一堂に並べ、ペンを握りながら所定の席で待機しているあいだ、森のカメラはオウムの指導者が記者会見の準備をしている隣りのスペースにすっと移動する。そして、テレビがその生の現実をどのように再加工し、お決まりのように教団にとって不都合な方向に話を展開させるのかを見ることになる。同時に、森はオウムの信者を同情的に描きながらも、彼らの非を問わぬことにはしていない。その辺の線引きがうまいし、倫理的な態度もわきまえている。


これに沿うかたちで、森は『A2』で普通の日本人を登場人物のなかに取り込んでいる。映画では、オウムと3つのグループ、すなわち警察、横暴な右翼国粋主義者、そしてオウムが活動する地域の住民たちとの接触が、そのあいだを縫うようにして描かれていくのだ。『A2』では2000年の始まりの時期を拾い上げ、それが物語の転換点に据えられることになる。広報部長の上祐史浩が出所し、麻原彰晃の息子たちに代わり指導者となるのである。教団はアレフと改名し、教義の変更を宣言。謝罪を行い、被害者補償のための大規模な基金を創設した。同時に、政府はオウム新法を制定し、当局の過剰な監視を可能にする。そして、全国のオウム施設の所在地では、地域住民が24時間体制の監視所を設置し、教団信者の動向を調べ上げる。
森は、こうした一連の動きを施設や組織の内部から追っていく。森の人間味あふれるまなざしが、教団員が受けるヒステリーや差別の実態を浮き彫りにしていくのだ。森は常に批評的で、何度でも被写体に挑みかかっていく。だがその接し方には敬意と親しみがこもってもいる。監視所の住民が教団信者と交流するうちに、世界が彼らを悪魔化するのがいかに不当であったかを知り、友好関係を築いていく光景にも同じことがいえよう。残るは極右の活動家、警察、メディアだが、いずれも学習を行って変化する能力はみられない。
今世紀に入ってから、森は『A』と『A2』で提起した複雑なテーマについて、何十冊もの本を書きあげてきた。人権、宗教と言論の自由の法的基盤と文化的課題、ジャーナリズムの実践における倫理的な難問などがそれである。いくつかの著書では、ドキュメンタリーと真実の証言をめぐって理論的な側面から力強い考察を展開している。これらは、彼が最新のドキュメンタリー映画『FAKE』(2016)と『i–新聞記者ドキュメント–』(2019)で再び取り上げているテーマであり、必見である。最近のこれらの映画で彼が目指しているものを理解するには、森自身の出発点である、『A2』に収められたメディア・スペクタクルの震源地を通してアプローチするのが理想的であろう。
(高橋恵 訳)

マーク・ノーネス
ミシガン大学アジア映画学教授。専門は日本映画、ドキュメンタリー、翻訳論。1990年代以降、YIDFFのプログラマーとして活躍し、映画も制作している。最近の著書、オープンアクセスの『Brushed in Light』では、書き文字と東アジア映画の密接な関係について論じている。
http://www-personal.umich.edu/~nornes
マーク博士の山形あれこれ:
http://www.yidff-live.info/tag/drmarkusyamagatamusings/
第1回『映画の都』監督:飯塚俊男/1991/ YIDFF ’91 特別招待
第2回『阿賀に生きる』監督:佐藤真/1992/YIDFF ’93 優秀賞
第4回『丸八やたら漬 Komian』監督:佐藤広一/2021/YIDFF 2021 やまがたと映画
第5回『新しい神様』監督:土屋豊/1999/YIDFF ’99 アジア千波万波
最終回『うたうひと』監督:酒井耕、濱口竜介/2013/YIDFF 2013 スカパー! IDEHA賞
![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](http://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)

