Yearly Archives: 2019
SPUTNIK — YIDFF Reader 2019
窓越しの自画像——『自画像:47KMのスフィンクス』と『自画像:47KMの窓』|結城秀勇
境界線上の記録——『ミッドナイト・トラベラー』『トランスニストラ』『十字架』|阿部宏慈
死者の声を聞く——王兵『死霊魂』|土屋昌明
田舎町という制度——フレデリック・ワイズマン『インディアナ州モンロヴィア』|斉藤綾子
喜劇を作るということ——蘇育賢『駆け込み小屋』|吉田未和
日常の底深くから——ガッサーン・ハルワーニ『消された存在、__立ち上る不在』|多田かおり
音楽に潜む政治的要素——『アナトリア・トリップ』『さまようロック魂』|山本佳奈子
映画と音楽の新たな波が出会うとき——ペレイラ・ドス・サントスとジョビン|石郷岡学
二重につきはなされること——『空に聞く』『二重のまち/交代地のうたを編む』|富田克也
ある台風の日に——草野なつか『王国(あるいはその家について)』|冨樫森
「ブラック企業」入門——土屋トカチ『アリ地獄天国』|滝口克典
歴史の忘却から目覚め、帝国という共通の祖先と向き合う|アニュエル・ヤン
あとに残された者たち——『島の兵隊』|キャシー・ジェトニル=キジナー
イラン現代芸術の拠点「カヌーン」の軌跡|ショーレ・ゴルパリアン
リアリズムの密輸業者、カムラン・シーデル|ジャン=ミシェル・フロドン
メカスさんの思い出とボレックス|小口詩子
磁気テープのシネマテーク——『チャック・ノリス vs 共産主義』『あの店長』|Murderous Ink
静かなる反逆者たち——『木々について語ること〜トーキング・アバウト・ツリーズ』|井上布留
来るべき日本文化映画批判のために|藤井仁子
新台湾ドキュメンタリーへの手引き|邱貴芬
インド北東部視聴覚アーカイブの創世記|ジュニシャ・コングウィル
記憶の橋を架ける——映像アーカイブの未来|梅木壮一
「やまがたと映画館」によせて|成田雄太
こけしの郷愁|梅木直美
「映画の都」の30年とこれから|小林みずほ
改造するひと、たむらまさき|鈴木一誌
1月24日の金曜上映会〈閉ざされた時間〉
今回の金曜上映会は〈閉ざされた時間〉と題して、山形国際ドキュメンタリー映画祭開催初期の90年代のインターナショナル・コンペティション上映作品から2本をお届けします。ドイツ、シビル・シェーネマン監督の『閉ざされた時間』。スロヴァキア、ドゥシャン・ハナック監督の『ペーパーヘッズ』。どちらも35mmフィルムでの上映となります。
『閉ざされた時間』 14:00-、19:00-(2回上映)
『閉ざされた時間』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 ’91 インターナショナル・コンペティション 山形市長賞(最優秀賞)受賞
監督:シビル・シェーネマン/ドイツ/1990/90分
作品紹介:
ベルリンの壁が崩壊する前、この映画の監督であるシビル・シェーネマンとその夫は、社会主義国家の権威と法を無視したという理由で、実際に逮捕され懲役一年の判決を下された。彼らはその前に国を出ることを願い出ていた。1985年、二人は西ドイツに追放された。そして今、ドイツの再統一の後、この監督はカメラをもって、あの時起こった事柄を分析し、理解するためにその地に戻る。彼女はいろいろな質問の答を得ることができるであろうか。彼女は判事、役人、弁護士など、その時彼女の運命を定めた人々を追跡する。そこには無数のボルトで堅く締められた扉や門がある。開いているものもあり、通過不能な壁として閉じたままのものもある。暗い廊下と錠のかかった監房は重苦しい閉所恐怖症の印象を刻む。監視員の鋭い目は絶え間なく私たちを虐げる。これは国家の専横さ、報復、厳重な支配についての映画である。これはまた、無力さ、盲目に服従すること、責任感の欠如について問う作品である。上からの命令は、質問することなしに即座に実行しなければならないというはかりきれないほど巨大な国家機構の中で、人間は単なるちっぽけな歯車にしかみえない。
YIDFF ’91 公式カタログより
監督のことば:
そして私はついに、前にいた刑務所の監房の一つに腰をおろし、はじめてその時抱いていた感情に耳を傾け、肉体的、精神的に私を苦しめた人々に会った。が、彼らは何も知らずにただ義務を果たしていただけという事実をひきあいにだして、自分たちは不正というギアで動いていた小さな歯車に過ぎなかったと主張した。その時、私は、本質を追求し、私と対立しようとした人々を見つけだそうと決めた。莫大な量の情報を見つけたが、ほとんどの人は昔のことを思い出すことができなかったり、思い出したくなかった。そして誰も「はい、今なら分かります。私はあの頃あなたに危害を与えました」といわなかった…ただ命令を受け遂行した人々、上の者の“必要性”に従った人々、何が起こっているのかさっぱりわからなかった人々、私はこのドイツの入り組んだ人間関係の中に、再び捕らえられたことを悟った。
シビル・シェーネマン
『ペーパーヘッズ』 15:50-(1回上映)
『ペーパーヘッズ』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 ’97 インターナショナル・コンペティション 優秀賞受賞作品
監督:ドゥシャン・ハナック/スロヴァキア/1996/96分
作品紹介:
この映画は1945年より1989年までのチェコスロヴァキアの歴史をまとめた作品である。膨大な記録映像を編集した内容、また生存者の証言には1945年以降のこの国の内情を知らなかった観客にとって数々の新事実が知らされることになる。だがドゥシャン・ハナック監督の視点は、さらにそれらの激動の時代を生き抜いてきた人々、より個人的な人間としての想い、感性の在り方に向けられている。自由な発言が得られず投獄された人々、今、晴れて暗黒の時代を語る生存者はしかし既に老人となっている。最早、失われた時は取り戻せない。それはしかし、取材をするハナック監督にとっても同じことであった。1989年当時、まだ社会主義諸国が解体する前に本映画祭に出品された『老人の世界』(『百年の夢』)は老人たちの死生観を独特なアイロニーで捉えた記録映画であったが、今にしてみればあの映画は作者が『ペーパーヘッズ』で込めた当時の体制への率直な批判を婉曲に表現した、またはせざるを得なかった仮面劇ではないかとも思われてくる。そこにハナック監督の芸術家としての一面を見る思いがする。私はもう一度『老人の世界』を見直さなければならない。『ペーパーヘッズ』は記録映像で写される犠牲者、証言者と同時代を生きた監督の深い心の傷を見る思いのする映画である。
YIDFF ’97 公式カタログより
監督のことば:
この映画は人権の蹂躙についての、そして全体主義体制下における市民と権力との関わりについての、エモーショナルなコラージュである。ソビエト帝国は第二次世界大戦の直後、“地上の楽園”を約束してその支配を拡大したが、その実践においては民主主義のあらゆる要素を拭い去り、恐怖とデマゴギーの政府を導入し、何十万もの人々の命を破壊したのである。
私の映画はより公正な世界で生きたいという人々の願いを描いたものであり、決して単なる過去の回顧ではない。共産主義支配は1989年に崩壊し、多くの国々が再び民主主義への道を模索している。これは矛盾に満ちた苦難の過程である。私から見れば、我々は過去との折り合いをつけることができず、我々の実際の生活は未だ過去の名残りがたくさん生き延びている。この映画では冒頭と最後に、1990年のメーデーで、共産主義時代の演壇に立った“ハリボテの面”(ペーパーヘッズ)を被った人たちを見て笑い声をあげるスロヴァキア市民たちの姿を見る。
この映画はそれをさらに突き進めた形で、共産主義時代からのプロパガンダの資料映像と、全体主義体制の犠牲者たち自身の語る証言の2つのレヴェルを交錯させる。そして最後に、我々は民主主義への戦いがまだ終わっていないことを学ぶのである。
ドゥシャン・ハナック
『ペーパーヘッズ』
[会場]山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室 [料金]鑑賞会員無料(入会金・年会費無料) [主催]認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 [問い合わせ]電話:023-666-4480 e-mail:info@yidff.jp
1月10日の金曜上映会〈パレスティナ:我々のものではない世界〉
2020年最初の金曜上映会は〈パレスティナ:我々のものではない世界〉と題して、パレスティナに関する2作品を上映します。バスマ・アルシャリーフ監督の『私たちは距離を測ることから始めた』、マハディ・フレフェル監督の『我々のものではない世界』。2本続けてお楽しみください。
14:00-、18:30-(2作品2回上映)
『私たちは距離を測ることから始めた』
『私たちは距離を測ることから始めた』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 2011 アジア千波万波上映作品
監督:バスマ・アルシャリーフ/パレスティナ、エジプト/2009/19分
作品紹介:
ローマ=ジュネーヴ、ガザ=エルサレム、物理的な都市間の距離を測る謎の集団、そして測られた距離が示される。その数値が、やがて政治的な意味を帯びていく過程。既視感のあるパレスティナのイメージに、「神の声」のナレーターの声が覆いかぶさり、パレスティナの複雑なナショナリズムを浮かび上がらせる。豊穣な音とテクストが何層にも重なり、不思議と連続性を帯びてくる映像は、やがてパレスティナの寓話へとつながっていく。
監督のことば:
私の作品は政治的問題を探究するものであり、そこでは内容を読解するための視覚的構造において独自に生み出したコードを用いる。幻影と幻滅、真実と陰謀、事実と歴史といった概念が、さまざまな形で現われる。焦点の中心といったものはない。物質的情報を多様な方法で読解しうる、ある言語、ある空間を作り出していき、情報を理解するためというよりも、経験するための手段を探っていくことが、これらの問題についての私の探究だ。
創作に影響を与え、動かしていくにあたっては、住んでいる環境、これまでの自分の経験に依っている。ある風景が、または都市環境がどのように機能しているかについての、書かれざる言語に私は注目する。場を規定し、構築しているものは何か。その場で、あるいはその場との関連で、人は他の人とどのように関係しているのか。物語がどのように機能するか、及びどのように操作されるかを描くにあたり、私が形式的構造として用いたのは、言語、ビデオ、フィルム、テクスト、写真である。そして私は、個人のアイデンティティや主観的経験との関連で、歴史および政治を表象するという実験を試みた。
公と私、政治と個人、フィクションとファンタジーの間にある余白に、私は関心を持っている。言葉がイメージへと変わること、イメージが物質へと変わること、作品の中のさまざまな層がサウンドによって立ち現われることも、私の関心の対象だ。私の制作活動において最も重要なのは、特定の場、特定の文化、あるいは特定の媒体からさえも、作品を切り離したいという衝動である。特定の政治的問題や、きわめて濃密なイメージ、陳腐なフッテージ、詩的なテクストを取り上げ、これら全てを定義されざるもの、物質的なものへと変えること。そして、全く共通点のない諸要素を合わせて新たな情報を生み出すことに、私は興味を持っている。
バスマ・アルシャリーフ
『私たちは距離を測ることから始めた』
『我々のものではない世界』
『我々のものではない世界』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 2013 インターナショナル・コンペティション ロバート&フランシス・フラハティ賞(大賞)受賞作品
監督:マハディ・フレフェル/パレスティナ、アラブ首長国連邦、イギリス/2012/93分
作品紹介:
北欧に移住したパレスティナ難民の監督が、かつて住んだレバノン南部のパレスティナ難民キャンプに里帰りするたびに撮影した映像と、父の残したホームビデオなどを織り交ぜ、家族や友の歴史、難民キャンプの変貌を、素直な語り口ですくい上げる。パレスティナの置かれている悲劇的な状況が、当事者でもなく、完全な第三者でもない視点から紡がれていく。タイトルは1972年に暗殺されたパレスティナ人作家、ガッサン・カナファーニーの小説名からとられている。
監督のことば:
私にとってこの映画を撮ることは、記憶を創造し、そして保存するうえでの意識的な試みだった。パレスティナ人、特に故郷を追われたパレスティナ人は、ひとつの民族としてのアイデンティティと集合的記憶が、つねに攻撃に晒されている。そのため、ただ記録を残すという行為でさえ、我々の存在を消さないための戦いの一部となる。
我々にとって、忘れることはすなわち存在するのをやめることだ。記憶は、たとえ日常生活のささいな記憶であっても、我々が存在する唯一の証拠である。
記憶する、また記録するという義務を、私は祖父から、そしてとりわけ父から受け継いだと感じている。父はまるで取り憑かれたように、家族の日常のすべての瞬間を映像に残していた。父の情熱が私に感染し、そして私は今ここで、父の残した映像をもとに、パレスティナ人として存在すること、それ自体を描き出す。単に紛争と苦しみについての記録であるのではなく、より人間的な物語だ。
マハディ・フレフェル
『我々のものではない世界』
[会場]山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室 [料金]鑑賞会員無料(入会金・年会費無料) [主催]認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 [問い合わせ]電話:023-666-4480 e-mail:info@yidff.jp
12月20日の金曜上映会〈イランを見る〉
今年最後の金曜上映会のテーマはイラン。山形国際ドキュメンタリー映画祭 2019 においても、イラン特集「リアリティとリアリズム:イラン60s—80s」は会場を埋め尽くす多くの観客の皆さんにお越しいただき、大変な好評を博しました。これまでも、これからも目が離せないイラン映画から2作品をお届けします。男性には自由意志による離婚が認められ、女性にはその権利がないイランで、「妻」が離婚を申し立てることの難しさを描く、キム・ロンジノット、ジマ・ミル=ホセイニ監督の『イラン式離婚狂想曲』。テヘランの公園の片隅でゴミとともに暮らす女性ミーナーを見つめた14日間を描く、カウェー・マザーヘリー監督の『ミーナーについてのお話』。2作品続けてお楽しみください。
『イラン式離婚狂想曲』 14:00-、19:00-(2回上映)
『イラン式離婚狂想曲』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 ’99 インターナショナル・コンペティション上映作品 国際批評家連盟賞受賞
監督:キム・ロンジノット、ジバ・ミル=ホセイニ/イギリス、イラン/1998/80分
作品紹介:
その建物には2つの入り口がある。一方には、肩を怒らせ階段を駆け上がる男たちの姿があり、もう一方には、チャドルに身を包み、俯いて歩む女たちの影が揺らめく。性差によるダブルスタンダードを隠そうともせず、むしろ誇示するかのような家庭裁判所の威容は、イランという国家の重層的な差別の構造を象徴し、その深淵に分け入る女たちの苦悩を垣間見せる。
YIDFF ’99 公式カタログより
監督のことば:
サルマン・ラシュディが姿を隠して以来、英国のテレビではイランに関する数多くのドキュメンタリーやニュース報道が放映されました。どれも硬派の時事番組で、殉教者の母親たちや革命守衛隊、アヤトラやファトワーを取材していました。ほぼ同じ頃、キアロスタミなどイラン人監督による劇映画も英国で公開されるようになりました。これらの映画は、普通の人々についての、詩的で、おだやかで、パーソナルな作品で、これら2種類の映像作品群は、まるで別の国からやってきたもののようでした。私は、イラン女性を個人としてとりあげ、英国の観客が他人事でなく親しみを感じることができるような長編映画を作ろうと決意しました。そんな時ジバに出会い、彼女の離婚裁判所における研究のことを聞き、理想的な主題だと思いました。この映画を撮るための許可を得るのに2年半かかりました。
キム・ロンジノット
『イラン式離婚狂想曲』製作のアイディアは、1996年、キム・ロンジノットと私が出会った時に生まれました。私たちは2人とも、西洋のメディアによるイスラム世界のステレオタイプ的な観方に不満を感じていました。また、キムはずいぶん前からイランを舞台にした映画を作りたいと希望していました。キムは、イスラム法のもとでの離婚を扱った私の本『Marriage on Trial』を読んでいて、そのテーマで映画をつくろうと提案してきました。イラン人であり文化人類学者の私は、彼女の提案を歓迎し、一緒に映画を作ることにしました。
ジバ・ミル=ホセイニ
『ミーナーについてのお話』 15:40-(1回上映)
『ミーナーについてのお話』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015 アジア千波万波 特別賞受賞作品
監督:カウェー・マザーヘリー/イラン/2014/54分
作品紹介:
テヘランの公園の片隅でゴミとともに暮らす女性ミーナー。ラジオニュースが流れるなか、新年の喧噪をよそに野良犬と戯れ、夜は焚き火の周りで、クスリや煙草を求めてくるホームレスとたわいない会話を交わす。そんなミーナーにも、夫と暮らし、身ごもった子どもを死なせた過去があり、普通の生活を送る夢がある。いまや犬やホームレスたちのゴッドマザーとなっているミーナーを見つめた14日間。
『ミーナーについてのお話』 監督のことば:
母が死んだのは、私が9歳のときだった。母の死後、父は私たちを置いて家を出ていった。残された兄と私は、二人だけで生活していかなければならなかった。その父も8年後、私が17歳のときに他界した。それから2年が経ったある日、一族の集まりがあった際、父が公園で物乞いをしているのを見たことがあると話してくれた人がいた。それ以来、もう何年もずっと、ひとつの問いが私の頭に浮かび続けている。「どうして父は私たちを捨てたまま戻ることなく、路上生活をする羽目になったのだろう?」。こうして私は、ホームレスについての映画を作ることになった。
『ミーナーについてのお話』は、父の人生という謎を掘り返そうとする試みである。ミーナーと出会ったとき、私が何年も探し求めていたものを、彼女が持っているに違いないと確信した。ミーナーとは、テヘランの公園で希望を秘めた生活を送っている女性なのだ。
正月休みの間、私はミーナーのところに行くことにした。イランのほとんどの人々が家族や友人と楽しく過ごしている、そんな時期に。半年前からミーナーのいる公園に通いつめ、彼女や他の人たちとも話をしていたので、友人と呼べる関係にはなっていた。
私はカメラのスイッチを入れて、ただ観察したものを記録しようとした。ひたすら見るだけでなにも干渉しない、それで父に対する執着への答えが見つかればいい、事前に決めていたのはそれだけだ。私の執着にも小さな変化があった。現在は、ミーナーがこんな環境から抜け出そうともせずに生きているのはなぜかという疑問がさらに加わったのである。
カウェー・マザーヘリー
『ミーナーについてのお話』
[会場]山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室 [料金]鑑賞会員無料(入会金・年会費無料) [主催]認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 [問い合わせ]電話:023-666-4480 e-mail:info@yidff.jp
12月13日の金曜上映会〈香港、台湾、2014〉
今回の金曜上映会は、香港と台湾に焦点を当て、真の民主主義を求める運動の様子を捉えた2作品を上映します。香港「雨傘革命」の闘いの現場を追い、活動家たちの揺れ動く思いを見つめる『革命まで』。中台サービス貿易協定の撤回を求めて学生たちが台湾立法院を占拠。複数のドキュメンタリー映像作家たちが様々な角度からこの「占拠」運動を包括的に捉えた『太陽花(ひまわり)占拠』。まさに現在進行形で揺れ動く民主主義を求める運動の現場を映した貴重な2作品です。
『革命まで』 14:00-(1回上映)
『革命まで』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015 アジア千波万波特別招待作品
監督:郭達俊(クォック・タッチュン)、江瓊珠(コン・キンチュー)/香港/2015/174分
作品紹介:
香港で民主的な選挙を求め不服従を呼びかけた「セントラル(金融中心街)を占拠せよ」運動は、思いを同じくする多くの学生や市民を巻き込み、その動きは2014年、「雨傘革命」として世界に広く知られるところとなった。本作は、運動内での議論、路上アピール、市民投票、学生らが主体となった政府庁舎前での抗議など、闘いの現場をつぶさに追い、渦中にいた7人の活動家たちの揺れ動く思いを見つめていく。
『革命まで』 監督のことば:
「革命」と呼ぶ人もいれば「大袈裟だ」と思う人もいる。「革命」の定義についての議論に結論はない。しかし民主主義を求めた香港の人々のこの闘いが、歴史的な出来事であることに疑いの余地はない。ドキュメンタリー作家として、自分が構えるカメラのすぐ前で展開する出来事が、まさに歴史そのものなのだと気づいた時、複雑な気持ちがこみ上げてきた。二人だけのチームでこの出来事を詳細に記録するのは限界があり、困難を極めた。それでもこの作品が、香港に真の民主主義をもたらそうとする人々をとらえ、今後の議論に貢献できることを祈っている。
郭達俊(クォック・タッチュン)
『革命まで』 「雨傘運動」が社会に与えた衝撃は、徐々に日常生活から薄れてきている。しかし私の脳裏には未だに劇的な場面が浮かんでくる。悲しい場面もあり、歓喜に満ちた場面もあった。この映画プロジェクトに関わっていなかったら、「雨傘運動」の受け止め方は変わっていたかもしれない。私にとってドキュメンタリー映画を制作することは、コミュニケーションと発見をしていく過程だ。活動家と話をし、その話を聞くことによって、この運動の複雑さと、その原動力について学ぶことができた。だからこそ「雨傘運動」の中で起きた衝突や決定の揺らぎをより深く理解し、受け止めることができたのだった。ドキュメンタリーとは、未来のための記憶でもある。私は、自分たちの時代を記憶に留めておく必要のある年齢になった。この作品が、79日間におよんだ占拠のなかで満ちあふれていた希望、香港で真の民主主義を達成するための長い道のりの、痕跡となることを願っている。
江瓊珠(コン・キンチュー)
『革命まで』
『太陽花(ひまわり)占拠』 18:30-(1回上映)
『太陽花(ひまわり)占拠』 山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015 アジア千波万波特別招待作品
監督:太陽花運動映像記録プロジェクト/台湾/2014/120分
作品紹介:
2014年3月18日、中台サービス貿易協定の撤回を求めて学生らが台湾立法院に突入、以後24日間にわたり議場占拠が繰り広げられた。立法院内の議論、床に寝泊まりする日々、NGO団体・学生・支援者らの抗議活動、権力側の暴力への抵抗は膨大な量の映像として記録され、それらは1988年の520農民運動や90年の野百合学生運動とも重ね合わせられる。家族に反対されながら参加した学生たちの声、研究者や警察官の告発……。作品には多くの独立系映像制作者が参加し、様々な角度から占拠を包括的に捉えている。
『太陽花(ひまわり)占拠』 監督のことば:
若者たちが、通用口から台湾立法院に突入したことで、底なしのブラックホールへの扉が開かれた。民主主義とは、そのブラックホールのように、つかみどころのないものだったのだ。それまで民主主義のシステムを享受してきた世代が、民主主義が奪われようとしていることに気づき、それを取り戻すべく奮闘する。この映画は、若者による太陽花占拠の運動、およびこれら若い運動家たちが、どのように民主主義と正義の価値を再考察したかを追った、涙と笑いの記録だ。
ドキュメンタリー映像作家たちは、「占拠」運動の英雄たちの物語を伝え、彼らが群衆を前にして感じた不安を描き、民主主義に向かいあっていかに無力だと感じたかを明らかにしようとカメラを撮ったのだった。
太陽花運動映像記録プロジェクト
『太陽花(ひまわり)占拠』
[会場]山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室 [料金]鑑賞会員無料(入会金・年会費無料) [主催]認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 [問い合わせ]電話:023-666-4480 e-mail:info@yidff.jp
山形国際ドキュメンタリー映画祭 2019 にてアジア千波万波部門の最高賞である小川紳介賞を受賞した『消された存在、__立ち上る不在』について、惜しくも映画祭への参加が叶わなかったガッサーン・ハルワーニ監督からいただいた受賞コメントを公開いたします。
アジア千波万波 小川紳介賞 『消された存在__立ち上る不在』
授賞式にて読み上げられたガッサーン・ハルワーニ監督のコメント全文
2011年、この映画製作をスタートした頃、とても嬉しいお誘いが舞い込んできました。小規模でも先鋭的な「ヒロシマアートドキュメント」という毎年開催されるアート・イニシアチブの展覧会に、私の初期作品を携えて参加しないかと。 広島市内を歩いていると、歩道に矢印が描かれていることに気がつきました。私の足を爆心地へと向かわせるかのごとく、その地点が爆心直下から何メートル離れているかも示されていました。
そこへは行かないと心に決めた私は、行かざるべき理由をあげては自分に言い聞かせ続けました。
しかし、それから2週間ほど経ったある日、ぼんやりと歩いているうちに、いつのまにか私は原爆ドームの前にいました。 それが何なのか、理解するまでに少し時間がかかりました。
そこで目にしたのは、原爆が炸裂した瞬間に石に刻まれた人の影。1945年、この場所に人がいたことの証を唯一示す形跡でありながら、その人の証は何も残っていないことを、私は思い知らされたのです。
この出会いが、『消された存在__立ち上る不在』という映画の概念的構造を形作るバックボーンとなりました。
この作品が、山形で上映される知らせを受けた時、大変嬉しく思いました。そして今、あらゆる時間と空間の不協和を超えて、強い共鳴が起きたことに、深く心動かされています。
この場にいないことが残念です。 ありがとうございました。
ガッサーン
山形国際ドキュメンタリー映画祭2019 では、サポーターのジェイムズ英会話さんとのコラボレーション企画として、日頃英会話を学んでいる子供たちが海外からのゲストへ英語でインタビューを行うイベント、その名も「目指せ!バイリンガルレポーター!世界の監督に突撃インタビュー!」を開催しました。
インタビュー前日の10月12日(土)、映画祭会場の山形市中央公民館(アズ七日町)隣りのジェイムズ英会話山形校 に集まった子どもたちは、まず、監督にどんなことを聞きたいか考えました。そして、それを英語ではどのように言うのか、ネイティブの先生方に教わり、翌日のインタビュー本番に向けて各自自宅で練習を重ねました!
10月13日(日)インタビュー当日、お昼ころに山形市民会館大ホールに集合した子どもたち。
まず最初に突撃したのは、こちら。
VIDEO
マレン・ビニャヨ監督(ラ・カチャダ )Cachada–The Opportunity_ )
しきりに一生懸命質問するキッズレポーターをかわいい!かわいい!と褒めてくださり
その近くをインタビュー終わりで通りがかった二人目の監督に突撃!
VIDEO
マレン・ビニャヨ監督(『ラ・カチャダ』 )理性 』)Cachada–The Opportunity _)Reason _)
Why do you make films ? という質問におお〜!と笑顔になるアナンド監督。
次は、赤いストラップを目印に声をかけたら・・・
VIDEO
ルネ・サワーさん Lune Sauër光に生きる ― ロビー・ミューラー 』)Claire Pijman (Director of _Living the Light–Robby Müller _)とともに映画祭に参加していた娘さん。
だんだん自信がついてきたキッズリポーター。その勢いのままに次へ!
VIDEO
映画を見に来ていた監督を入り口でキャッチ!「5分だけならいいよ〜」とインタビューに協力してくれたのは、ミコ・レベレザ監督(『ノー・データ・プラン 』)Miko Revereza (Director of _No Data Plan _)。とても気さくに、キッズにも好きな食べ物を質問してくれたり、最後にハイタッチしてくれたり。キッズの緊張がどんどんほぐれていきました。
市民会館大ホールでは上映が始まって人がいなくなったので、隣のフォーラム山形へ移動しようとしたところ、オープンカフェで休憩していた バフマン・キアロスタミ監督(『エクソダス 』)Bahman Kiarostami (Director of _Exodus _) をキャッチ!レポーターと監督の身長差がすごい!一つの画面になかなか収められなかったのですが、二人をなんとか画面に入れようと撮影も頑張ったキッズレポーター!ぜひ御覧ください!(撮影もキッズが iPad で行っています。)
VIDEO
バフマン・キアロスタミ監督(『エクソダス 』)光に生きる ― ロビー・ミューラー 』)ある夏のリメイク 』)Exodus_ )Living the Light–Robby Müller _)Remake of A Summer )
市民会館大ホールでQ&Aを行っているという情報をキャッチして向かう!
その後、再度フォーラム山形に向かうも、途中のカフェでまたもや赤いストラップ発見!セヴリーヌ・アンジョルラス監督!台風一過で晴天なものの風の強い屋外でしたが、笑顔で「私も英語上手じゃないので一緒よ〜」「みんな英語上手ね!」と全員からの質問に丁寧に答えてくださいました。
ようやくフォーラム山形に到着!早々にキャッチしたのは・・・
VIDEO
ジジ・ベラルディ監督(『山の医療団 』)カナカナブは待っている 』プロデューサー)Beyond the Salween River _)Kanakanavu Await _)
だんだんアドリブが効くようになってきたキッズレポーター。ロンナンプロデューサーに納豆は好きか聞いたところあまりお好きじゃないと。逆に君たちは納豆好き?と聞かれ「あんまり。。。」と答えると握手を求められる場面も。心が通じ合ったようでした。
VIDEO
張齊育(テオ・チーユー)監督(『ここへ来た道』)
だんだんみんな積極的になって、一人がインタビューを終えると僕も僕もと前に出て質問できるようになりました。用意していた質問をするのも飽きたのか(?)だんだん本当に自分が聞きたいことを英語で質問するようになって、日頃の勉強の成果を発揮していました。
ジョン・トレス監督にオススメのグルメを聞かれて「玉こんにゃく」と伝えるも、「こんにゃく?それは何?」の質問にキッズもスタッフもあたふた。こんにゃくってどう説明したらよいのー!(監督、食べればわかります!)
VIDEO
章梦奇(ジャン・モンチー)監督(『自画像:47KMの窓 』)アナトリア・トリップ 』)Self-Portrait: Window in 47 KM _)Anatolian Trip _)
ジョン監督へのインタビューの様子を「かわいい〜!」と撮影していたジャン・モンチー監督。もちろんそのままインタビューを受けていただきました!
最後はみんなで記念撮影。
地球の反対側から届いた、若者たちの思い
教育を受ける権利を守るため立ち上がるブラジルの高校生たちを描いた「これは君の闘争だ」。山形国際ドキュメンタリー映画祭2019での上映では大きな反響を呼び、優秀賞を受賞しました。
山形の高校生はこの作品をどのように受け止め、どのような問いを監督に投げかけたのでしょうか?
インタビューの様子 _ この映画は、リズミカルな語りと音楽が印象的でした。なぜテンポのいい音楽を取り入れたのですか。
この映画を撮り終え、高校生たちに90分という尺を伝えると「そんなの長すぎる!」という反応が返ってきました。そこで普段映画を見慣れない高校生を退屈させないよう、アクティブな要素が欲しいと思い、リズミカルな音楽を取り入れたのです。この映画には3人の主人公が登場しますが、私は4人目の主人公がいると思っています。それは音楽です。あるシーンで音量が大きすぎる、何を言っているのかわからないと言われたことがありました。しかし、私としては、そのシーンは音楽が存在を主張していい所で、むしろもっと音量を上げるべきだと思いました。
_作品のなかで同性愛者の方が描かれていましたが、なぜそのトピックにクローズアップしたのですか?
LGBTを映画で取り上げたのは、それが自分自身を表現する武器だからです。男女関係に限らず、誰とキスをし、誰を愛するのかというのもすべて自分が考えることです。この映画には2人の女の子がでてきます。そのうちの1人はこの学生運動に参加していなかったら、彼女はいつになっても女性を好きになるという自分に気づけなかったと思います。デモという場は、そこに参加する若者たちにとって安心して自分を表現することのできる空間でした。
私もかつてフェミニズム運動に参加したことがあります。その時に出会った1人の女の子が露出の多いぴちぴちの服を着ていました。私はつい母親になった気持ちでその子に「ちゃんと服を着なさいよ」と声をかけてしまいました。そのとき彼女は、「私に触れないで。これは私の身体。私がなにを着ようと、どうやって私を表現しようとそれはあなたには関係ない」と答えたのです。私は黙り込んでしまいました。やっとそこで自分はなんて失礼な質問をしたのだと気づきました。それから、自分の映画にもジェンダーのことを取り入れることで自分の個性を表現する場を見せたいと思うようになりました。
世界的にLGBTというのは重視されてきています。しかしいまだにブラジルでは、カトリックの伝統に反しているという理由で殺される人もいます。だからこそ、若い世代の人たちから、より強い意思をもって発言していく運動をするべきです。私もこの映画を通して、LGBTも一つの個性だということを伝えたかったのです。
_多様性というのも作品の一つのテーマだと思いました。多文化社会を築くにはどのような事が必要だと考えますか?
ブラジルには日本とは比べられないくらいのたくさんの歴史があります。その一つに奴隷制度がありますが、廃止されたのは19世紀後半のことにすぎません。だから、人々の間には差別意識がいまだ根強く残っています。
多文化社会のなかで多様な価値観に触れることで、自分はどうありたいのかを考える事ができるのだと思います。また、自分の考え方や社会に対する考え方、人に対する思いやりを考え直す事ができます。若い頃の私は両親の言うことを鵜呑みにしていましたが、サンパウロに引っ越してさまざまなバックグラウンドの人々と話していくうちに、両親とは異なる考えを持つようになりました。周りの意見がカラフルであればあるほど自分の意見もカラフルになれるのです。
「これは君の闘争だ」の一場面。強権的な当局に対し情熱とユーモアをもって立ち向かいながら、若者たちは仲間を見つけ、自分を表現する喜びを見出してゆく。 _ブラジル国内での上映ではどのような反響がありましたか?
非常に感情のこもった反応でした。特にサンパウロでは大きな劇場が満席になり、熱狂的な雰囲気に包まれました。観客の中にはマルセラの祖母や母親もいました。もともと娘の運動への参加に否定的だった彼女たちも、映画を観終わった後にはマルセラの行動に理解を示し、「あなたを誇りに思う。愛している」と繰り返し伝えていました。そのとき私は、家族の絆が深まるのを感じました。
今後この映画が、運動収束後に高校生となった学生たちに当時のことを伝えるとともに、急速に右傾化しているブラジル社会の人々に運動を振り返らせ、政治に対する一人一人の意識を向上させるのに役立つことを期待しています。作品はテレビでの放映も決まっており、どのような反応が起こるのかも楽しみです。
_監督が考える理想の教育とはどのようなものでしょうか?
良い学校というのは、生徒一人一人が個人として尊重され、何を学ぶのかの選択肢が与えられる学校だと思います。数学が好きな生徒は数学を、哲学が好きな生徒は哲学を追求できるというように。そして自分自身を愛し、大切にすることのできる、安全な環境を整えることも大切です。そのために学校の先生には、生徒と同じ目線に立って話をしてほしいと思います。
スマートフォンで簡単に情報が手に入る時代ですが、大事なのは好奇心を持って世界と向き合い、この世界をよりよい場所にしようとする情熱です。学校が生徒に求めるべきは既成の問いに対する答えではなく、自ら問いを立て、考える姿勢だと思います。
インタビューを終えて、記念撮影 _最後に、日本の高校生にメッセージをお願いします。
変わること、なにかを変えること、そして自分の意見を言うということを恐れないでください。そして考えたうえで、自分の意見があるなら、きちんと表現の仕方を考えましょう。この映画の主人公たちがデモを始めた当初、政府は別に目を向けてくれませんでした。そこで彼らはそれ以上のことをしないと私たちの話を聞いてくれないと気がつき、クレイジーな戦略を編み出して運動に持ちかけました。
監督として伝えたいのは、とにかく勇気をもって自分の夢を追いかけること、自分を見つけることです。誰に何を言われようが自分の意見があるのだったら、それを絶対発言してください。それは仲間を見つけることで実現できることもあります。一人で発言してもどうしても声が届かないことがあるのです。だから仲間を見つけて、自分の意見を出し合っていくことが大切だと思います。
また、社会をより良い、より包摂的なものにしようとする世界中の運動からアプローチの仕方を学ぶのも必要だと思います。そうすることで自分のやり方を見つけられるかもしれません。とにかく勇気をもって行動すること、変わることを恐れないこと。それを心がけていると、生きている意味を見つけられるでしょう。
ただし、このような運動をする上では自身の安全を守ることが一番大切です。「勇気をもちなさい」と私は言いましたが、それは自分を大事にすることも意味します。暴力を振るわれトラウマになってしまわないように、自分の身をなにより大切にしてください。
_ありがとうございました。
インタビュアー:結城晴花、齋藤公佑、齋藤亮佑、長澤パティ明寿
埋もれる者たち
ガッサーン・ハルワーニ『消された存在、__立ち上る不在』
米倉伸
行方不明者たちに、死は訪れるのであろうか。
30年以上前にレバノンで勃発した内戦のため、レバノンでは多くの行方不明者が出た、と本作の冒頭付近で背景が説明される。レバノンでの「行方不明者」は、その生死や安否が不明である限り、戸籍上は生存し続けるという。
あるポスターが繰り返し映される。夥しい数の行方不明者たちの顔写真が整然と並び、真ん中に大きく“MISSING”と書かれている。その数の多さから写真の一枚一枚は切手ほどの小ささとなり、もはや遠目からの個人の判別は困難を極め、それはさながら「模様」――映画の中で使用される言葉を借りるなら「市松模様」――と形容した方が腑に落ちるほどである。
試しにガッサーン・ハルワーニ監督がその「市松模様」から一枚の写真を切り抜き、それが誰であるかと試しに尋ねてみても、誰もその問いに答えられない。しかし、その顔写真がポスターの一部に戻ると、即座にこう答える、「“彼ら”は行方不明者である」と。その瞬間に彼ら「行方不明者」は「個」を喪失してしまうのだ。
あまりにも大きな悲劇は、むしろその被害の甚大さゆえにしばしば当事者にとってさえ「非現実的なもの」となり、人々の関心を奪っていくのかもしれない。それを証明するかのように、街角に張られた件のポスターは、徐々に別のポスターや広告などに上塗りされ、埋没し、人目に触れない不可視の領域に消えていく。
三十年余りに渡って形成され、もはや地層とも言える程に積み重なったそれらの張り紙を掘り起こし、再び「行方不明者」(の「個」=写真)を発見しようとする企ては想像するだに途方もない。具体的には、監督がそのように積み重なった張り紙の層をカッターで「掘り進める」作業が延々と映し出されるのだが、そこで費やされる時間の長さに、もうこの作業の終わりは来ないのではないかとすら思えてくる。
レバノンの街では、時折、集団墓地が出土するという。しかし、その墓地から上がった遺体は、公人たちからの埋め直し指示により隠蔽され、それが誰であるかといった情報が特定されることはない。監督がポスターを掘り起こす作業は、本作のキャメラでは撮影されることが無く、ただテレビやラジオの報道などを介して伝えられる集団墓地の挿話への対応、あるいは抵抗ではないかと。
執拗な作業の様がクローズアップで映され、ポスターの顔や情報がスクリーン上に克明に可視化されるとき、彼らは「行方不明者」という「群」から離脱し、名前を再び与えられた「個人」となる。
埋め直しにより不可視化された彼らの存在は、その瞬間に「不在者」としての可視化を果たす。「行方不明者」の生死が不明である限り、今後彼らに何かしらの形での死(あるいは生)が降りかかるかもしれない。この映画が時と共に不可視(invisible)になってしまわないことを切に願う。
フィルムの解体と再生
ヤシャスウィニー・ラグナンダン『あの雲が晴れなくても』 ジョイス・ラム
35mmフィルムが流れるように引っ張られる。見慣れない特製の木の枠が地面に置かれていて、その枠を通過したフィルムの少し先でハサミが待ち受ける。その刃先を通すとフィルムのパーフォレーションが切断される仕掛けになっているのだ。映画愛好者にとっては非常に驚くべき振る舞いや装置ということだろうか。しかし、それは上映するためのフィルムではない。ボリウッド映画が刻まれたフィルムの一コマ一コマが、ピンク色の竹の棒に次々と挟まれていく。その棒を回すと小さなオルガンのようにガタガタと音がする。“キャトケティ”という子ども用おもちゃの製作工程だ。
キャトケティの視点を通して私たちの世界を見つめるかのような本作は、その生産地であるダシュパラというインドの小さな村へとまずは観客を誘う旅の映画でもある。ご飯を作ったり、昼寝をしたり、テレビを観るといった日常生活を送るおもちゃ作りの職人たちの現実に、赤いルビーを探し出そうとする子どもたちの虚構のストーリーが織り交ざる。
働く人たちの手と、キャトケティを作るための道具に焦点を当てる。職人たちは竹林で伐採した竹を棒状に切り取り、三日月の形をした刃物でその先に切り込みを入れたうえでピンク色に染色、フィルムを切り込みに挟んで竹の先を輪ゴムで綴じる。そうした一連の作業での職人たちの手さばきは疑いようもなく洗練されており、その作業から生じる音がリズムよく耳に響く。まるでこの村ならではの独自の「音楽」の演奏が始まろうとしているようだ。思い起こしてみると、確かに、ハエが飛んでくる音や、船が湖を通過する音、風の音など、この映画のサウンド・デザインは非常に豊かで印象的だ。上映後のQ&Aでのヤシャスウィニー・ラグナンダン監督の話を聞くと、映画に登場するボリウッド映画のフィルムに記録されたサウンド・トラックまでもが密かに活用され、本作の豊かな音環境に忍ばせてあるらしい。
一見淡々とした日常生活のなか、彼/彼女らは次々とフィルムを本来の形から変形させ、そこに新しい役割を吹き込んでいく。一方で、この映画を通して作り手は、村の住民によって素材(=物質)としてしか認識されないフィルムを、元の形態、すなわち映像(=シネマ)に戻そう(reverse)としているようにも感じられる。映画を通して度々画面上に現われる、フィルムの劣化による錆びた鉄のような模様や、フィルムを村の空間に実際に投影するシーンなど、彼女はこの村に関与しながら「シネマ」としての新たな表現まで作り出そうとしている。使用されなくなり、いったん物質になったフィルムが、新たにおもちゃ(キャトケティ)として生まれ変わり、さらにそれが映画(シネマ)への再生を果たすことで人を楽しませる力を保ち続けるのだ。
インターナショナル・コンペティション 審査員:オサーマ・モハンメド(審査員長)、ホン・ヒョンスク、サビーヌ・ランスラン、デボラ・ストラトマン、諏訪敦彦
総評
ロバート&フランシス・フラハティ賞(大賞)死霊魂 』監督: 王兵(ワン・ビン) フランス、スイス/2018/495分
「人間の本質」に分け入って行く稀有な叙事詩である。映画の本質に分け入って行く稀有な叙事詩である。存在はもっとも強力な証拠である。映画が歴史を呼び覚ます。
山形市長賞(最優秀賞)十字架 』監督: テレサ・アレドンド、カルロス・バスケス・メンデス チリ/2018/80分
この映画は新しいドキュメンタリーの形の可能性を切り開く。その力は、その倫理と高貴さゆえのものだ。過去が蘇り、未だ正義がなされていない現代に取り憑く。木で作られた十字架が森に立てられるというシンプルなフォルムがこの亡霊たちに与えられるとき、我々は今なお世界を変えられる映画を信じるのだ。
優秀賞 ミッドナイト・トラベラー 監督: ハサン・ファジリ アメリカ、カタール、カナダ、イギリス/2019/87分
2019年に出会った最も強烈なオデッセイである。監督と家族は、命を懸けた危険の中でもスマートフォンで記録し、ついには映画を作り上げた。時には映画が人生の最も切実な瞬間を捉えることができると証明してくれた監督に敬意を表する。待つことの退屈さと恐怖の時間を巧みに描いたこの作品は、新しい形の特別なロードムービーを提示してくれる。
優秀賞 これは君の闘争だ エリザ・カパイ ブラジル/2019/93分
これは自由への運動を追う映画である。ブラジルの学生たちの闘いは、映像と声の流れを産み出し、そこに音楽的な拍動と明確に言うべきことを言う喜びを発見する。傍若無人にして明晰な、集団による提示が、まさに我々のこの時代を語る。
審査員特別賞 インディアナ州モンロヴィア 監督: フレデリック・ワイズマン アメリカ/2018/143分
賢明なる人物(ワイズマン) がひとつのコミュニティの身体と魂にCTスキャンをかける――インディアナ州のモンロヴィアという街だ。寛大さとアイロニーに彩られたユニークな映画言語が、社会そのものが恒常的に共同で形成し続けているさまざまなステージを提示して行く。この映画言語は、そこに映し出される全てに通底する悲劇を思い起こさせつつも、あくまで決してそれを名指しすることなく、我々自身がその認識に自力でたどり着けるだけの広がりを与えてくれている。
アジア千波万波
審査員:楊荔鈉(ヤン・リーナー)、江利川憲
総評
小川紳介賞 消された存在、__立ち上る不在 ガッサーン・ハルワーニ レバノン/2018/76分
消えた人々の存在が監督の手によって少しずつ明らかにされてゆくに従い、人々は真相へと一歩近づく。生者が死者を代弁するように、監督はシンプルな映像と自分だけの意志で、人類に共通する経験と命題を描き出す。死者よりも恐ろしいのは、生者の沈黙と隠蔽である。
奨励賞 ハルコ村 サミ・メルメール、ヒンドゥ・ベンシュクロン カナダ/2018/100分
カメラは私たち観客を監督の故郷へと導き、村の留守を預かる人々の息遣いや、女性に共通する宿命を、間近に体感させてくれる。一年また一年と待ちわびる時間の中で、彼女たちの生命には粘り強くしなやかな自我の成長の刻印がきざまれていく。
奨励賞 エクソダス 監督: バフマン・キアロスタミ イラン/2019/80分
この作品は、小さな窓を通して人々の辛さや苦しみ、様々な人生模様を描いている。帰郷の路はあまりに遠く、彼らの置かれた境遇とその当惑は理不尽な秩序に縛られている。
市民賞
『死霊魂 王兵(ワン・ビン) フランス、スイス/2018/495分
日本映画監督協会賞
審査員:内藤誠(審査員長) 、竹林紀雄、水谷俊之
総評
『気高く、我が道を 』 イラン/2019/64分
『気高く、我が道を』は1979年の革命により、イランでは女性のみならず、男性が女装して踊ることも禁止されたという事態に基づくドキュメンタリーである。 だが、踊ることを愛する80才の男性は、牛を飼い、農作業をしながら、いまも機会を見つけては、女装してダンスをしている。
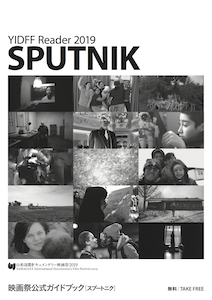
![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](http://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)

































