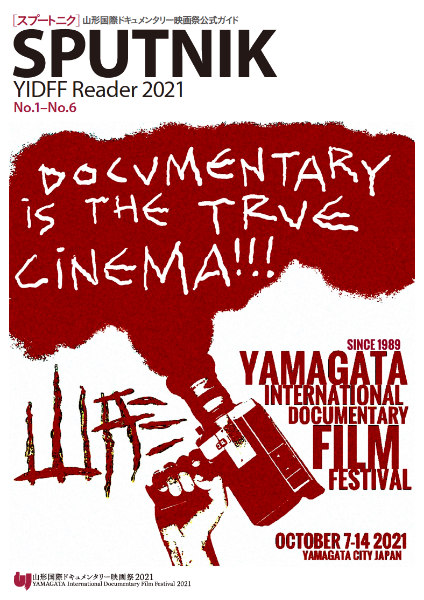Yearly Archives: 2021

『炭鉱たそがれ』監督:陳俊華(チェン・ジュンホア)
山本佳奈子
「中国」「炭鉱」、この2つのキーワードが並ぶと、ジャ・ジャンクーがいくつかの映画で描いた炭鉱夫の悲運や、実際に起こった炭鉱内連続殺人事件を題材に描かれた劇映画『盲井』(リー・ヤン、2003年)を思い出す。過酷な環境で使い捨てられる炭鉱夫、炭鉱内で起こる犯罪、炭鉱管理者の横領等の問題が噴出した2000年代から2010年代以降、多くの映画監督や作家が中国の炭鉱を描いてきた。映画『盲井』は、中国当局の検閲を通過せず上映禁止となったが、国外や台湾で大きな評価を得た。中国の炭鉱にまつわる諸問題は、地上の光にさらすことが難しい。
『炭鉱たそがれ』は、カメラを向けられることを拒否する炭鉱夫のカットから始まる。メインの被写体となるこの男は、国有企業の炭鉱で働く炭鉱夫であり、監督の父でもあり、カメラを向けてくる息子にうんざりしている。被写体が「撮るな」と言っているうえに、舞台はタブー多き中国の炭鉱だ。緊張感ある導入に身構えてしまう。
観る者を緊張させたまま、カメラは炭鉱夫たちが炭鉱に入場する様子を映し、さらに、リフトで地下800メートルまで潜る。リフトに乗った炭鉱夫たちががやがやと雑談する声がうっすらと聞こえる中、リフトが降下する音が響き、壁が下から上へ猛スピードで流れていく。ワンカットで見せる映像の臨場感により、こちらの鼓膜内の気圧もおかしくなってしまいそうだ。
暗い坑内に出ると、炭鉱夫たちが狭い通路を行き交い、作業している。多くの作業が機械化され、炭鉱夫たちの防塵マスク着用も徹底しているようだが、坑内でのスリやトラブルの危険性について炭鉱夫たちが雑談する場面で再び緊張が走る。
場面が地上に戻ると、近くの別の炭鉱で爆発事故が起こり幾人かの炭鉱夫が死亡したことがテレビで報道される。続いて、映画の舞台となった炭鉱でも、人員整理という名の大規模リストラの話が伝わってくる。石炭不況のあおりをうけて、国の方針が変わったことが原因だという。リストラされるのは、出稼ぎへ行った実母の代わりに監督を子供の頃から育てた後見母らだ。リストラ通告を受けた者たちは、国有企業の割には補償額が少ないと怒り、集まって話し合う。一部の者は天安門広場での抗議を企てようとするが、皆の事情はバラバラで、抗議活動への熱意が煮え切らない。
監督自身がカメラを回し、父や後見母、友人、そしてその周辺の炭鉱で働く人々を主な被写体とするこの映画は、2014年から2019年までの約6年間で撮影されている。時が経つにつれて撮られることに慣れたのか、被写体たちがおおらかにありのままに自ら語り出すようになるのが興味深い。炭鉱のシリアスな諸問題を受け継ぎながらも、映画後半では家族愛や友情にフォーカスが当たるようになる。例に漏れず、監督の父もカメラの前で次第に饒舌になっていて、前半の緊張が解けてホッとする。監督の後見母となった女性が自宅で見せる柔らかな表情も、リストラに怒る前半での彼女と対照的だ。そういえば、この約6年のあいだに、中国ではSNSや動画サイト、ショート動画が爆発的に流行した。多くの人が「撮られる」ことに慣れた期間に撮影されたということも、被写体のカメラ慣れを加速した要因のひとつだろう。終盤になればなるほど、カメラは被写体との距離を縮めていく。ある陽気な炭鉱夫は、ネットが身近な告発の手段にもなり得るということを知ってか知らずか、「ネットにあげてくれ!」とカメラに笑顔で言い放つ。
石炭不況や炭鉱での労働問題を追いつつも、現代中国の労働者それぞれが抱く不安や悩み、幸福観や価値観の差異が見えてくる。同じ労働者と言っても、ひとまとめにすることは難しく、家庭の事情も思想もバラバラだ(だからこそ、抗議活動では団結できなかった)。監督はそこに着目し、映画後半では被写体たちの人間性をおさえることに集中したのではないか。例えば若い炭鉱夫の友人は、撮影期間中に最初の子供が産まれたにもかかわらず、終始不安そうな顔しか見せない。炭鉱夫という職業の未来を憂慮しているのだろうか。また、出稼ぎに出て家族と別れて暮らす監督の実母は、感情に任せて怒りと悲しみを家族にぶつけるシーンにのみ登場し、客観的な背景や家族の事情について映画の中で説明されることはない。説明を控え、その代わり被写体に近づき感情や表情の部分に照準を合わせることで、炭鉱を取り巻く人々を一般化してしまわず、ひとりひとりの個性ある人間として映し出すことに成功している。
映画の最後には、カメラマンを兼任した監督も自ら被写体としてカメラの前に座り、饒舌な父と一緒に映像に収まる。父子の会話にこれといって感動的な要素はないが、撮る側と撮られる側としての約6年間の関係の末に、家族としての距離が最も縮まった場面だ。『炭鉱たそがれ』は、炭鉱問題を通して、家族の関係を見つめ直す映画なのだ。

『蟻の蠢き』監督:徐若涛(シュー・ルオタオ)、王楚禹(ワン・チューユー)
浦野真理子
『蟻の蠢き』は、中国最大の国有通信会社チャイナテレコムを解雇された56人の労働者たちの権利申し立てと、彼らを支援する20数名のアーティストたちと1人の弁護士の活動の記録だ。あかぬけない農村の中高年労働者たちは、年金と未払い金、そして法の公正な執行を求める。インテリのアーティストたちは、芸術の社会的な役割を自らに問い、アートを通じ労働者の訴えを一般に届けようとする。政治的な迫害の危険はすぐそばにある。当初、両者に存在していた隔たりはだんだんと埋められ、草の根のダイナミックな政治運動になっていく。
まず画面に映し出されるのは、陝西省の山あいに鳥の声が響く遠景ショット。のどかな光景に見えるが、カメラが右にパンをしていくと、険しい山並みがどこまでも続く。舗装された道路に車が行きかう北京の路上を映す画面を挟み、広くはないが観葉植物が飾られ、居心地の良さそうな中産階級のアパートの居間に場面が移る。ワン・チューユー監督を含む10名ほどの男女のアーティストたちがソファーと椅子に車座で座り、真ん中に置かれたコーヒーテーブルに置かれたスナックをかじりながら話している。この討論会のテーマは、アートパフォーマンスを行い、統制されたメディアの代わりに労働者の訴えを一般に知らせることの意義について。芸術が労働者に奉仕する理念を実現しようと、監督らを乗せた車はいくつものトンネル道を抜けて陝西省へと向かう。ホテルの一室での両者の会合の様子を見る限り、労働者たちはアートパフォーマンスの説明にピンときていない。しかし会社前で行われた街頭デモでは、アーティストたちに指示されるまま、饅頭をくわえた特大写真を掲げる抗議パフォーマンスを行う。饅頭は生存のために必要な食料を象徴的に表し、パフォーマンスを通じ老齢年金を要求している。しかし社員からの妨害に合い、2人の労働者が1週間警察に拘留されてしまう。
この映画に出てくる労働者たちは、20年以上も陝西省でチャイナテレコム社に雇われ、バイクで山道を行き来して電話線敷設や保守点検業務を担ってきた。しかし会社側は中高年になった彼らを2018年に突然解雇し、契約は労務請負で雇用関係はなかったと主張。年金を払わないばかりか、彼らが自腹で立て替えた経費や客からの未回収金さえ清算しようとしない。北京での請願も聞き届けられず、裁判に訴えるが雇用か請負かが焦点とされ勝算は少ない。
アーティストの理念と労働者の生活のニーズにはずれがある。労働者と家族のなかには、逮捕を警戒し、アーティストたちの活動に困惑する者もいる。ある労働者の妻は夫の活動に「自分は最初から反対。地道に暮らせばいいのよ」と言う。しかし、その妻が、別の場面では赤いすてきな服を着てメイクアップし、アーティストと労働者の集まりで得意の歌を披露する。監督が労働者とともに占い師を訪ねる場面もおもしろい。訴訟の見込みを「悪くない」と言う男性の占い師に訴訟に縁起の良い日を挙げてもらい、皆で機嫌よく帰っていく。そんな些細なエピソードが描かれるにつれて、アーティストと労働者の波長が合っていくように見える。
他方で、政府と法律の正統性についてアーティストと労働者の考えがすれ違う現状をあらためて浮き彫りにする場面もある。ワン監督は労働者ととともに「中華人民共和国労働法」を読み合わせるパフォーマンスを行う。上からスポットライトが照らされたスタジオ。労働者たちは労働法を読み、労働争議調停委員会は会社側の人間で構成され労働者の味方ではないことを確認する。床に何冊もの労働法の本がばらまかれている。監督は自分の指を傷つけ床に置かれた本に血を垂らす。一冊の本が上下を逆にした状態でカメラに大写しになると、監督はその本の各ページに血を塗りつけ、さらに一冊の本を手に取り突然ページを引きちぎり、口に入れる。1枚、2枚、3枚。そのまま飲み込んでしまうのかと思いきや、うめいて紙を吐き出す。監督は、本を床に投げつけ、何が法律だ、こんなもの役に立たないと吐き捨てるように言う。困ったように監督を見つめる労働者たち。労働法の本を破るのは過激すぎる、法律は公正で執行する個人に訴えたいだけと苦言を呈する。そして、監督が破り捨て紙くずとなった本の横で、労働者たちは労働法を読み続け、書いてあることを理解しようとする。それは共産党の本来の理念実現への願いでもあるだろう。方向性や考え方の違いこそあれ、両者が同じ問題に真剣に取り組む事実を告げる鮮烈な場面だ。
映画の終盤、50代半ばで亡くなった仲間の家で、労働者らが遺影を前に涙を流す。胸に白い花をつけ、花輪で墓を飾り爆竹を鳴らしてお参りをする。強い風が吹くなか、寒々とした風景が労働者たちの無念を表しているようだ。風の音がいつまでも鳴り続ける。
労働者たちが求める補償は最後まで得られない。ラストで中国語による「インターナショナル」の素朴な歌声をバックに、労働者たちの名前と一人一人の上半身裸の写真が映し出される。労働者たちの写真はあくまでも田舎の中高年らしく、その体は、長年の労働や困難に負けず仲間と一緒に権利を訴えてきた事実を無言のうちに物語り、彼らに対する監督の敬意を表している。それらに混じるワン監督とアーティストたちの上半身裸の写真は、彼らと仲間として活動してきたことへの誇りと連帯のしるしのようだ。

『自画像:47KMのおとぎ話』監督:章梦奇(ジャン・モンチー)
山本佳奈子
おとぎ話とは空想の物語のことであり、現実の記録ではない。この作品は、現実を投影するはずのドキュメンタリー映画でありながら、現実と相反するとも言える「おとぎ話」をテーマに置く。ではこの作品が映すものは、ドキュメンタリーで捉えられるべき現実なのか、それとも空想なのか。
北京を拠点とする映画作家で振付家の章夢奇(ジャン・モンチー)が10年間撮り続ける、中国のとある田舎の農村。彼女は、親戚たちが住むこの村に「47KM」という名前を付け、そこを舞台に映画『自画像』シリーズをこれまでに8本制作してきた。
9本目となる今作の中で章夢奇は、47KMに家を建てたいと話す。殺風景な平原の向こうに見える丘に、青い家を建てるという。その家には、庭があり、野菜畑があり、踊りの舞台があり、図書室もある。庭には椅子とテーブルを置き、村の人たちが集まる公共のスペースになるのだ、と。彼女は、このまるでおとぎ話のような夢を、47KMに住む親戚の子供たちに伝え、その家の絵を描いてもらう。まだ学校にあがっていない小さな子供、小学生、中学生(あるいは高校生も)、さまざまな年代の子供たちは、真冬の枯れ草で覆われたその丘に集まる。自らの希望も加えながら、青い家の完成図を想像し、画用紙に家と庭を描く。子供たちが熱心に描く絵は、色彩に乏しい真冬の枯れ草の上にあってもカラフルで、想像力に富んでいて、大人である我々が子供たちからおとぎ話を聞かせてもらっているような、楽しい情景だ。
青い家こそがこの映画のテーマであるおとぎ話なのかと思いきや、なんと、映画の中盤では、実際に建築工事が始まる。作業員たちが黙々と真剣な顔で建築作業を進め、レンガが積み上がり壁となっていく。子供たちは、寡黙な作業員たちの周囲でニヤニヤとしていて、おとぎ話の実現にほくそ笑むかのようだ。同じ画面に映る作業員と子供の、表情のギャップが面白い。
章夢奇が子供たちに語る青い家は、おとぎ話から現実に変化した。マジックのような展開の裏には、村の大人たちとの対話や、経済的な準備が必要だったことが推測できる。彼女の行動力に感嘆するとともに、おとぎ話を真剣に紡ぐことは、現実を変える力になりうるのではないかと考えさせられる。
映画全編に満ちた幻想的なおとぎ話の雰囲気に時おり冷気を吹き込むように、子供たちの祖母や祖父、大人たちは、子供に向かって現実を突きつける。子供の母親が出稼ぎに行ってしまったこと。大学に行くまであと何年かかるのか。学校にはきれいな服を着て行くようにという注意。おとぎ話の中に、このような厳しい現実が挟まれるのだが、それらの現実がなければおとぎ話は引き立たない。映画は現実とおとぎ話の世界を行ったり来たりして、どちらの世界に自分の視点を置くべきか、観客は迷子になりかける。しかし、最年長で16歳の女の子・方紅(ファン・ホン)が、抜群のバランス感覚で私たち観客をガイドしてくれる。今、大人と子供の狭間にいる方紅は、あるシーンでは現実を見据えた冷淡な言葉を放つこともあれば、別のシーンでは年少の子供たちと戯れ合う。もう10年間も彼女を撮り続けている章夢奇が、彼女をこのおとぎ話の大役に抜擢するのは当然だ。頼れるガイドである方紅は、章夢奇に手渡されたハンディカメラを手に、自身のおとぎ話の世界にも私たちを案内してくれる。
ただし、終盤に登場する夜の暗闇は、私たちを困惑させる。真っ暗闇のなか鶏を追いかけ回す大人たちを撮ったシーン。同じく真っ暗闇の建築途中の家で、過去の47KMでの映像を投影しながらそれに重なるようにして女の子たちが踊るシーン。突如挟まれたこれらの暗闇は、現実離れしている幻覚のようにも見えた。今見ているものは、おとぎ話なのか現実なのか。この場面に方紅のガイドはなく、私たち観客は、暗闇で路頭に迷うかのごとく右往左往してしまう。そして、白昼のシーンに戻ったとき、夢から覚めて再び現実に戻ってきた感覚を得る。
このように世界を行き来するうちに、おとぎ話と現実の違いなんて、そう大きなものではないのではないかと感じさせられる。大人が子供のために創作し、話し聞かせるおとぎ話は、現実に着想を得ている。どこからどこまでが現実で、どこからが作り話か? その境界は、作り手で話し手である大人にとっても時に曖昧だ。むしろ曖昧である方が、楽しめる。
おとぎ話と現実のあいだで迷子になる楽しさを味わえる、奇妙で幻想的な作品だ。そして、映画が終わる頃には、この青い家が本当に完成したのかどうかなんて、どうでもよくなってしまう。空想か現実か。どちらにいるのもいいじゃないかと、爽快さが残るのだ。

『私を見守って』監督:ファリーダ・パチャ
中川鞠子
電話の呼び出し音に続き、話しはじめる女性とその相手の声が、黒い画面を背景に耳に届く。やがて音に遅れを取って映し出される、事務所らしき場所でメモを取りながら受話器を持つ、先の「話しはじめる女性」……。こうした音の先行によって、私たち観客の「聴く」ことへの意識を喚起してはじまるファリーダ・パチャ監督『私を見守って』(2021)では、病院から独立して活動する、医師・看護師・カウンセラーで構成された3人の女性ケアスタッフ——病院の終末期医療への批判がたびたび映画のなかで聞かれる——が、患者の家を訪ねる形で行うインドの在宅緩和ケアの現場が捉えられてゆく。冒頭からの電話(=声)のやりとりがまだ継続されるなか、彼女たちが同乗する自動車内から捉えられた、それなりの都会であるらしい道路や街並みが画面に現れ、3人の患者の終わりが見えかけた人生を垣間見る旅に私たちは誘われてゆく。
医療行為の大前提は、患者の意志を最優先に考え、ケアを行うことなのか。本作においても、患者本人の意志にできる限り寄り添うべく、耳を傾ける患者家族やケアスタッフの姿がある。
最初に私たちが出会う患者は、家長である年老いた長身の男性だ。常に父のそばで寄り添う息子は、本人と母の前でガンのステージの話をしないよう、ケアスタッフに事前に求める。家族が病状や今後の方針を積極的にスタッフに問うなか、意識が朦朧としはじめているのだろうか、かつては快活であったことがうかがえる患者の男性は、どこか上の空である。
続いて、子供たちを村の祖母のもとに置いてきたという比較的若い男性患者。彼の肺がんは進行しているとはいえ、効きそうな経口抗がん剤があるとされる。しかし、その方が身体が楽だということで、いつも屋外で治療を受ける彼とその妻に、月に7万ルピー(日本円にして10万円強)の薬代を支払うことは難しいとされ、治療やケアはケアスタッフの手に委ねられることになったようだ。
最後に、排泄すら困難な状態で力なく横たわる年老いた女性患者。ケアスタッフはすでに何度かその家を訪ねているようだが、この映画ではじめて彼女と向き合う観客にいきなり提示されるのは、家族とスタッフとの間で交わされる、家で看取るか、病院で看取るか、といった究極の議論である。
3人の患者とその家族を待ち構えるのは、すべての生の終わりに約束された死であり、生きる以上、誰しもが直面する途轍もなく大きな問題だ。こうした問題を取り扱う作品は、これまでにも、そしてこれからも、様々なアプローチによって創造されてゆくだろう。それでは、「聴く」ことへの意識を強く喚起することではじまるこのドキュメンタリーがもたらす特異な体験とは何だろうか?
最初に私たちが出会った男性患者とその家族との間で交わされる印象的なやりとりが映画の後半にある。症状が進み、声が出せなくなってしまった患者は、身体の微細な動きによって自らの意志を伝えようとする。冒頭からの緻密な構成によって私たち観客に喚起されていた「聴く」ことへの意識は、その対象である声(=音)の喪失によって「観る」ことに転換されるともいえるが、それは同時に聴き取ることの困難な声、声ならざる声をそれでも聴こうとする無謀にして繊細な企てに収斂される。私たち観客も、朦朧とした患者の姿——彼の虚ろな目はそれでも何かを訴えている——をより真剣に「観る」ことになり、言い淀むような迷いを見せつつも、男性患者が伝えようとする声にならない声=意志を、常に寄り添ってきた息子とともに汲み取らなければならなくなる。それまで冷静さを装っていた息子は堪えきれずに大声をあげて泣き喚く。そこで老父が口にした声なき声の正確な意味合いは、私たちには判然としない。ただ、父親の声なき声=意志に耳を傾けることから、息子が泣き喚き、フレームアウトするまでをワンショットで捉えたこの長回しは、持続する時間のなかで変化する感情を見事に捉えている。朦朧とした父の姿にショットが切り替わってもなお、フレームの外から持続して耳に届く彼の泣き声は、真剣に「聴く」ことを欠いては闇に葬られていたかもしれない父の最期の声=意志の脆さ、その瞬間性を喚起する。二度と繰り返すことのできない瞬間の重なりをたしかに捉えたその長回しは、脆い意志がかろうじて守られた奇跡的なショットであった、と心からの感動を覚えずにはいられないのだ。
声なき人の声=意志を「聴く」ために「観る」こと。あるいは、何かを一心に「観る」ことで、聞こえてくるものの到来を真剣に待つ(=「聴く」)こと……。「観る」ことと「聴く」ことの相互作用によって脆弱な声=意志に寄り添い続けた人々の姿は、いつの日か訪れる「大切な誰かの死」に向き合う勇気と術を私たちに与えてくれるだろう。誰かとの別れが迫った時、たとえ声(=音)が不在であったとしても、「観る」ことと「聴く」ことを通して声なき声=意志を受け止めることのできる可能性が、私たちには残されるはずなのだ。

『ルオルオの怖れ』監督:洛洛(ルオルオ)
山本佳奈子
2020年1月、新型コロナウイルスが湖北省武漢市で発見された。パンデミックは中国を襲い、さらには世界にも広がった。武漢市がロックダウンされたのは1月23日のことだったが、この映画はその数日前の撮影から始まる。この映画の監督であり主な被写体でもあるルオルオは、自宅の薄暗い部屋にカメラを置き、マスク姿でカメラに向かう。彼女の顔がクローズアップになるが、口元はマスクに覆われていて見えず、目は怯えている。そして、不安に声を震わせながら独白する。ウイルスが恐ろしい、外出する気になれない、誰かが歩く音が聞こえれば窓を閉めたくなる、ウイルスは自分の心を侵食している、と。
ルオルオは、四川省南部の地方都市にある集合住宅に、90歳の父と同居している。その2人の住居で撮影された映像のみでまとめられる本作で、カメラは一歩たりとも外に出ない。コロナ禍という特殊な状況下で、高齢の父とすでに退職したルオルオが送る日常風景が、シーンの大部分を占める。三脚で設置されたカメラは2LDKほどの住居で過ごす父娘をとらえ、2人はすでにカメラの存在を忘れているかのようだ。
コロナ禍におけるルオルオの私日記とも言えるこの作品では、生活にルーチンが生まれるのと同様、定型のシーンが順々に繰り返されていく。ルオルオの独白、父との食事、家事、ルオルオがパソコンで参加する仲間のオンラインミーティングにオンラインヨガ、父の個人史の聞き取り。彼女が参加しているミーティングは、映画作家で振付家の章夢奇(ジャン・モンチー)らが参加するプロジェクト「民間記憶計画」の集まりのようだ。メンバーは中国各地に散らばっている。
映画内のルーチンに、地図で「民間記憶計画」メンバーの居住地を探し出す行為も加わる。壁に貼った中国全土地図に、ルオルオがカメラを向け、一人でぶつぶつと話しながらメンバーの居場所を探す。地図にズームアップし、見つかった都市名や県名を指でそっとなぞる。オンラインでしか今は会えない彼らとの関わりの実感を、身体的に得たいという渇望が滲み出る。
前述のように、父の個人史を聞く行為も、この映画のルーチンのひとつだ。父は、近づく死を意識して、コロナ禍の前から回想録を文章で綴っているという。数センチにもなる分厚い手書きの冊子に綴られているのは、1950年代に政府の失策によって起こった大飢饉や、反右派闘争の不条理と悲劇だ。ルオルオが当時のことを質問すると、父は歯に衣着せぬ言い方で政権を批判する。耳が遠く、普段から声が大きくなってしまうルオルオの父だが、1950年代当時を語るときにはさらに声が大きくなり、眼光にも鋭さが増す。約70年が経ったとしても、これは決して忘却されてはならないのだという主張を感じさせる。
映画全体に散りばめられているのは、記憶と創作というテーマである。まず記憶については、ルオルオが父の個人史に触れ、「民間記憶計画」に参加していることからも明らかだ。彼女は記憶というものの価値を重要視している。コロナ禍において、いかにウイルスを恐れたか、いかに他者と関わったか。彼女の私的な記憶を映画化したとも言えるのが、この作品だ。
そしてその記憶が、あくまでも創作行為として映画のフォーマットでまとめられているのが、単なる私日記を超えた面白さである。時系列のログではなく、ルオルオ独自の芸術的感性によって編集されることにより、観る者は、ルオルオの当時の感覚や記憶を、より生々しい状態で感知することができる。住宅内に差し込む美しい自然光やカメラを固定する位置の工夫、屋外から聞こえてくる雑踏の音やテレビ音声の効果、そしてルーチンで繰り返される場面展開から生まれる映画全編のリズム。これらの意図的な演出には、ルオルオが残したかった記憶の、言葉にならない部分が詰め込まれている。
当初は心が侵食されて神経質になり、不安に苛まれていたルオルオだが、映画の終盤で徐々に明るい表情を取り戻していく。サンルームに降り注ぐ陽光のもとで踊り、また、歌も歌う。このような彼女の変化も、ルーチンのようなリズムのある場面展開によって、より引き立てられた。
では、この抑圧された状況で、彼女はどうして自身に変化をもたらすことができたのか。映画を作るという創作行為によって、彼女は癒しを得たのではないだろうか。ちなみに、映画の中で彼女の父が朗読する回想録も、詩的で美しく、文学的センスに富んでいて、まごうことなき一種の創作なのだ。創作は、抑圧された精神に対して何らかの作用をもたらすのかもしれない。

『燃え上がる記者たち』監督:リントゥ・トーマス、スシュミト・ゴーシュ
浦野真理子
インドは最新のIT産業が発展する世界最大の民主主義国家だ。一方でカースト制度外に置かれ不可触民とされるダリトたちへの差別と暴力が根強くはびこっている。2002年、インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、ダリト女性たちの手で新聞カバル・ラハリヤ(「ニュースの波」)が創刊された。映画の前半では、その勇気ある報道がデジタルメディアという武器を得て大きな反響を呼ぶサクセス・ストーリーが主に展開される。
本作のヒロインの一人である、20代の主任記者ミーラが、レイプ被害の取材をする場面から映画は始まる。小柄だがしっかりした体を色鮮やかなサリーで包み、仕事道具のカバンを肩に下げたミーラが、家畜の鳴く声が聞こえる土づくりの家へ入っていく。4人の男に何度もレイプされたと被害を訴える女性の横で、苦しそうに黙って座る夫。被害届を何度出しても警察は対応しない。女性の夫はラハリヤ紙が唯一の希望だと語る。行政に声を届けられるジャーナリズムは民主主義の源だとミーラは語る。
カバル・ラハリヤの記者たちは24人の若く小柄なダリト女性たち。取材のための移動には、乗り合いタクシー、バス、列車など公共の交通機関が使用される。事務所の会議では皆で車座になって床に座る。彼女たちは貧しい家庭で育ち、字が書けなかったり、家に電気が通っていないメンバーもいる。しかし、彼女たちは表情豊かでやる気に満ちている。これまで暴力と差別で声を封じられてきたダリト女性たちが、ジャーナリズムを通じて力を得、先にミーラが語る信念を胸に、報復を恐れることなく勇気ある取材を続ける。
もう一人の記者スニータは、2004年からマフィアが違法操業を行う採石場近くの村の出身だ。スニータはミーラとともに作業員生き埋めの取材に訪れる。地上にぽっかりと空いた巨大な採石場を行き来するトラックとそこで働く子どもをはるか崖上から俯瞰する映像を背景に、10歳のころからこの採石場で小石を運び働いていたとスニータは語る。当初はマフィアの報復を恐れる作業員たちだが、ペンの力で人を守りたいというスニータの熱意に動かされて取材に応じ始める。
カバル・ラハリヤ紙は動画による取材とインターネットを介した配信を進める戦略をとる。スニータが採石場の違法操業を動画で流すと100万回再生され大きな反響を呼ぶ。ダリトたちの置かれた医療、道、水路、電気などの悲惨な現状への訴えが、デジタルメディアを通じ人々と行政に届き、次々と改善が実現する様子はまるで奇跡のようだ。
一方で映画は、ミーラたち記者たちが日常で経験する厳しい差別と内なる因習をも描いている。ミーラの娘が通う学校の出席簿には「家柄」を記入する欄があり、同級生にダリトであることを知られ、からかわれている。自分が独身でいることで親が世間の厳しい目にさらされることを恐れたスニータは、結婚しカバル・ラハリヤを退職することを決めてしまう。社会を変えたいと願う記者たち自身も、社会の構造を背負って生きているのだ。
こうして、ダリト女性たちの果敢な挑戦を描く映画も、次第に不穏な空気に包まれ始める。後半に進むにつれて、デジタルメディアが暴力的な右翼ポピュリズムも拡大させる諸刃の剣であることが示されるのだ。2017年、ウッタル・プラデーシュ州の州議会選挙はイスラム教住民を敵視するヒンズー至上主義勢力の勝利で終わる。
長い交渉の末にミーラが実現させた、ヒンズー自警団のリーダーである青年へのインタビューが印象に残る。質素な土づくりの部屋でミーラは三脚を立て、言葉を選びながら青年に問いを発する。農家出身で父が生活苦で自殺した過去を持つ青年は、イスラム系住民を敵視し、狂気じみた目でうっとりと剣をなでる。抑制された描写でありながらも、どこか戦慄を誘う鮮烈な場面だ。
2019年、モディ首相が選挙で再選を果たし、ヒンズー至上主義の勢いが止まらない。ラーマ神をたたえる盛大なパレードで飛行機から花が撒かれる。ミーラはパレードに参加する政治家にインタビューし、宗教の政治利用ではないかと問いかけるが、取り巻きたちに退けられてしまう。インドでは2014年から40人もの記者が殺され、真実の報道は報復と隣り合わせだ。ダリト女性たちのデジタルメディアによる訴えに好意的に反応した大衆もポピュリズムの罠に陥り、デジタル空間で得た勝利は束の間で失われていくかのようだ。しかし、退職を決めたスニータがカバル・ラハリヤに復帰することを決めた事実がテロップで示されるなど、映画は最後まで希望を手放そうとしない。それこそが、この映画の製作者を突き動かす信念でもあるのだといわんばかりに、ジャーナリズムは社会を映し出す鏡であるべきだ、とのミーナの声が、熱狂的なパレードを背景に私たちの耳に届く。
- SPUTNIK — YIDFF Reader 2021
-
No.1
- 四角い画面の内と外|畑あゆみ
- ヤマガタの巡礼者たちへ|フィリップ・チア
- 区切りを迎えた気分の先に|小川直人
- 失われるもの、引き継がれるもの―香味庵クラブという場|奥山心一朗
- 審査員は一人でも一丸でもない|マーク・シリング
- 牛をめぐる奇妙で不穏な旅―『彼女の名前はエウローペーだった』|日下部克喜
- ただ愛あるのみ―『ミゲルの戦争』|吉田未和
- 山形特選、この一品(1):銀山上の畑焼|石郷岡学
- ドローイング|ロックスリー
No.2
- 銃で奪った土地が銃になる―『核家族』|マーク・ノーネス
- 好奇心と発見|エドウィン
- カマグロガという一家とその土地をめぐるエスノグラフィ|アルフォンソ・アマドル監督に聞く
- 彼女たちの声を聞くということ―『ナイト・ショット』『心の破片』|渥美喜子
- 山形特選、この一品(2):ウッディファーム&ワイナリーの果物とワイン|井上瑶子
- 名もない歴史の破片のために―『きみが死んだあとで』|岩槻歩
No.3
- 彼女たちのメディア―『夜明けに向かって』『燃え上がる記者たち』『メークアップ・アーティスト』|伊津野知多
- フォーク・メモリー2020、そこにある怖れとちからとおとぎ話―『自画像:47KMのおとぎ話』『ルオルオの怖れ』|高昂
- 再び見出された、1970年代モロッコのアートシーン|アリ・エッサフィ監督に聞く
- 山形特選、この一品(3):壽屋寿香蔵の梅の砂糖漬け|戸田健志
- 映画はどこへでも届く|ジェイ・ロサス
- 集いの場―Playground Cafe BOXの試み|奥山心一朗
- ドローイング|ロックスリー
No.4
- コーディネイターたち―震災後ともにある方途を探し求めて|三浦哲哉
- 占領の記憶、消された町の記憶―『最初の54年間』『リトル・パレスティナ』|阿部宏慈
- 共に生きるための言語|ニシノマドカ監督に聞く
- 若さと孤独と|クレール・シモン監督に聞く
- 2021年、“BYT”について|前田真二郎
- 山形特選、この一品(4):酒井製麵所の生麵|鈴木伸夫
No.5
- 政治闘争における怖れの位置―『理大囲城』『怖れと愛の狭間で』|キャメロン・L・ホワイト
- 死にゆく人から目を背けずに|ファリーダ・パチャ
- 輸出されるベトナム人労働者―『異国での生活から』『駆け込み宿』の背景|秋葉亜子
- 未来の旅のみちしるべ―「やまがたと映画」によせて|黒木あるじ
- 山形特選、この一品(5):奥山メリヤスのニット|梅木壮一
- 夜明け前の子どもたち―『国境の夜想曲』|田中晋平
- かれら自身のためのフィクション―『国境の夜想曲』|田中竜輔
No.6
- 私たちが市長になるのよ!―『ボストン市庁舎』|結城秀勇
- 懐疑から肯定へ―『ボストン市庁舎』|クリス・フジワラ
- (再)発見の年|ルイス・ロペス・カラスコ監督に聞く
- 記憶と記録、私と公の狭間で―『スープとイデオロギー』|石坂健治
- 踊り子たちの淡々とした野性味―『ヌード・アット・ハート』|武藤大祐
- 山形特選、この一品(6):キャラクターから知る町の名産品|吉野美智子
- ドローイング|ロックスリー
![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](http://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)